目次
はじめに
「おまじない」と聞くと、
子どもの頃にやった恋愛成就のおまじないや、
受験合格祈願などを思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、日本におけるおまじないのルーツをたどると、
千年以上前の平安時代にさかのぼります。
当時、貴族たちは 陰陽師(おんみょうじ) に病気や災厄を祓ってもらい、
呪符や言葉を用いた「おまじない」で生活を守っていました。
この記事では、
✅ 日本最古のおまじないの歴史
✅ 陰陽師と呪符の役割
✅ 現代に受け継がれる形
✅ 実際に試した人の口コミ
✅ おすすめの開運グッズや関連本
などを徹底解説していきます。
日本で一番古い「おまじない」のルーツ

「おまじない」という言葉の由来は、古語の「まじなひ」で「呪い・魔除け」を意味します。
記録に残る日本最古のおまじないは、 平安時代の陰陽道 に大きく関わっています。
陰陽師とおまじない
平安京(現在の京都)では、陰陽師が暦や星の動きを読み、祈祷や呪符を使って人々の不安を和らげました。
特に有名なのが 安倍晴明。
彼は式神を操り、病気や災いを防ぐ呪術を行ったと伝えられています。
呪符(お札)の起源
陰陽師が使った「呪符」は、文字や図形を墨で書いた紙で、悪霊退散や病気平癒の力を持つとされました。
現代でいう「神社のお守り」や「お札」は、この呪符文化が形を変えて残ったものです。
平安時代に行われた代表的なおまじない
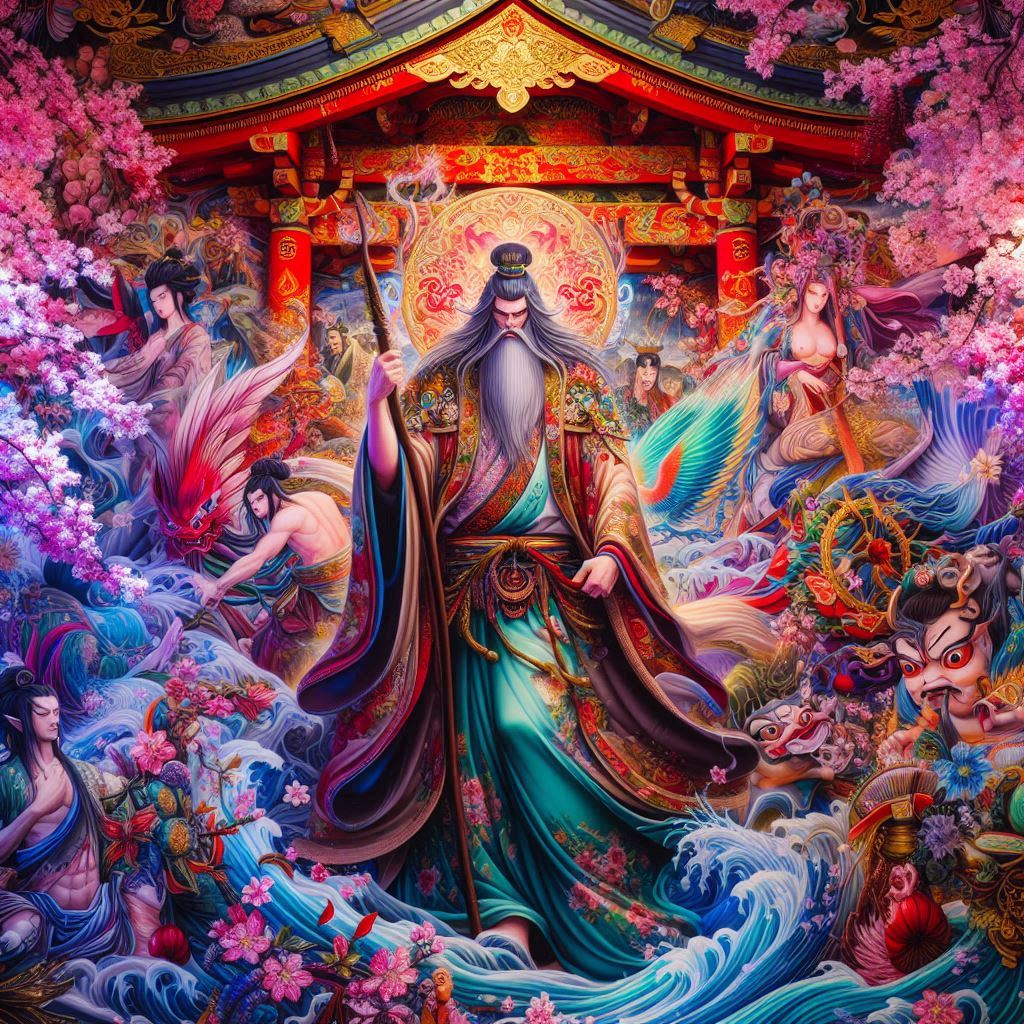
当時の記録から、いくつかの代表的なおまじないをご紹介します。
-
方違え(かたたがえ)
不吉な方角に行かないよう、宿を変えて災厄を避ける習慣。 -
御霊信仰(ごりょうしんこう)
怨霊を鎮めるために祭礼を行う。これが後の「祇園祭」に発展。 -
呪符・呪文
墨で書いた呪符を身につけたり、水に溶かして飲んだりして災厄を祓う。 -
言霊(ことだま)
言葉に宿る力を信じ、唱えることで現実を変えるとされた。
現代に残る「おまじない」の形

平安時代から千年以上たった現代でも、多くのおまじないが生活に根付いています。
-
神社のお守り・お札 → 呪符の進化形
-
厄払い・厄年の習慣 → 陰陽道の厄除け文化
-
初詣・おみくじ → 占いや吉凶判断の名残
-
合格祈願鉛筆・恋愛成就グッズ → 言霊・呪符の現代版
「日本で一番古いおまじない」は、形を変えながら今も私たちの暮らしに息づいているのです。
実際に試した人の口コミ
💬 「厄年に神社で厄払いを受けたら、大きな病気をせず無事に過ごせた」
💬 「受験前に合格祈願のお守りを買ったら、不思議と安心感があった」
💬 「京都で晴明神社に参拝してから、仕事が順調に進み始めた」
多くの人が「科学的根拠はないけれど、心の支えになる」と感じています。
おすすめの開運・おまじない関連グッズ

Q&A

Q. おまじないって本当に効果があるの?
A. 科学的に証明は難しいですが、「信じる心」が行動や心理に影響を与え、良い結果につながるケースが多いです。
Q. 自分で呪符を作ってもいいの?
A. 昔は陰陽師が専門でしたが、現代では神社仏閣で授与されるお守り・お札を大切にするのが主流です。
Q. 海外にもおまじない文化はあるの?
A. もちろんあります。西洋の魔女の呪文や、アジア各地のお札文化など、日本の呪符と似た風習が見られます。
まとめ
日本最古のおまじないは、平安時代の陰陽師が行った 呪符や祈祷 にルーツがあります。
-
平安時代、陰陽師は人々を災いから守る存在だった
-
呪符や言霊の文化は、現代のお守り・お札に受け継がれている
-
厄払い・祭礼・祈願など、今も日常に残る習慣は多い
おまじないは「信じる心」が最大の力。
現代の私たちも、千年前の人々と同じように、不安を和らげるために祈りを続けているのです。
